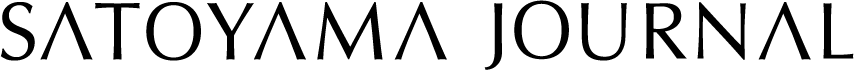新幹線(飛行機)でのアクセスについて
送迎はありますか?
チェックイン・アウト時の一日一便のみ、上越線大沢駅から送迎がございます。往路は14:30発、帰路は11:15発。東京方面へは下記の列車に接続します。なおそれ以外の時間は越後湯沢駅からの定額タクシー(4600円・冬季のみ5600円・前日までの予約制)が便利です。
東京・往路
東京駅12:40発(とき321号・新潟行き)越後湯沢駅13:56着
在来線乗り換え 越後湯沢14:16発(上越線・長岡行き)大沢駅14:26着
東京・帰路
大沢駅11:42発(上越線・水上行き)越後湯沢駅11:54着
越後湯沢駅12:11発(とき318号・東京行き)東京駅13:28着
越後湯沢駅からの定額タクシーはどのように手配すればいいですか?
ご予約確認メールに記載されたコンシェルジュデスクにお電話いただくか、メールをいただければ手配いたします。前日までにご予約ください。料金はタクシー運転手に直接お支払いください。
定額タクシーを依頼しました。乗り場はどこですか?
越後湯沢駅改札を出て20メートルほどの左手、西口出口の手前(駅構内)に「駒子像」(小説「雪国」の主人公の人形)があり、その前に「里山十帖」のプレートを持ったドライバーがお待ちしております。お名前を告げてご乗車ください。
近くでレンタカーを借りられますか?
里山十帖と里山十帖 THE HOUSE IZUMIの共用で、レンタカーを一台(車種:ジムニー AT車)をご用意しています。詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。ご希望の際はお早めにお問い合わせください。
なお上越新幹線の越後湯沢駅周辺には下記のレンタカーがあります。
トヨタレンタカー >>
ニッポンレンタカー >>
駅レンタカー >>
観光タクシーは手配できますか?
越後湯沢駅また里山十帖から出発する観光タクシーの手配が可能です。清津峡トンネルまでは約30分、見学時間も加味すると2時間程度の貸切になり、料金は普通車で13,800円、ジャンボで19,000円です。なお「越後妻有里山現代美術館 MonET(旧キナーレ)」や「まつだい農舞台」を巡るには4〜5時間が目安です。
ゆざわ魚沼タクシー
関西方面(名古屋)からはどうやって行ったらいいですか?
東海道新幹線に乗りやすい地域にお住まいの方なら、東海道新幹線+上越新幹線の乗り継ぎが便利です。東京駅での乗り換えは、乗車券と特急券を通しで購入しておくと「直通の乗り換え改札口」をご利用いただけます。直通の乗り換え改札口利用だとホームからホームまで2〜3分、乗り換えに10分もあれば余裕です。なお「EX予約」+「えきねっと」などのモバイル乗車券では直通の乗り換え改札口が利用できず、一度、在来線の駅構内に出てからぐるりと新幹線乗り換え口に回ることになります(なんとかならないものですかね?JRさん)。とはいっても乗り換えに要する時間は5〜6分。弁当などの買い物を考慮しても15分程度の乗り換え時間で大丈夫です。送迎に間に合う便は新大阪9:57発の「のぞみ88号」です。
伊丹空港が近い方なら、新潟空港経由も。伊丹10:20発「JAL2243便」を利用すると新潟空港11:20着。ANA1659便だと伊丹11:10発、新潟空港12:15着(新潟駅への所要時間は飛行機到着からおおよそ1時間です)。その後は新潟駅周辺で昼食をとって14:01発の「とき84号」で越後湯沢駅14:43着、越後湯沢からは定額タクシーをご利用ください。(新潟駅&空港方面からは大沢駅の送迎に適した乗り継ぎ列車がありません。大沢駅周辺には商店も喫茶店もないのでご注意ください)
そのほか、関西空港からはpeach12:05発、新潟空港13:20着もありますが、新幹線乗り継ぎで越後湯沢16:24着。里山十帖到着は17:00ごろになります。
その他の地域からはどうやって行ったらいいですか?
札幌(千歳)、福岡と新潟空港は複数便がありますので、「新潟駅周辺でランチを食べてから」「途中で燕三条に行ってみたい」という方には適しています。ただし圧倒的に便利なのは羽田空港+東京駅から新幹線利用。便数が多く、私たちも出張の際にはほぼ羽田空港を利用しています。
車でのアクセスについて
駐車場はありますか?
敷地内に無料の駐車場があります。ご予約は不要です。
早く着きそうなのですが、塩沢インターから里山十帖までの間に時間調整する場所はありますか?
塩沢石打インターを出た信号を左折したほうが里山十帖は近いのですが、このルート上にはコンビニもカフェもありません。早く着きすぎた時は右折して国道17号線に出てください。17号との交差点にローソン、国道沿いには道の駅があります。
EV充電機はありますか?
駐車場に2機の倍速普通充電機(6kW)があります。宿泊者専用で利用無料。原則的にチェックインからアウトまで1台専用なので、早めにご予約ください。TESLAの方はご自身で必ず変換アダプターをご用意ください(SAE J1772 アダプター)。
冬に車で行きたいのですが、大丈夫ですか?
12月から3月中旬までは必ずスタッドレスタイヤでお越しください。またシーズン数回の大雪の際には里山十帖への最後の道が4輪駆動車でないと登れません。大雪予報時は新幹線でのご来館をおすすめします(上越新幹線はどんなに大雪でも止まりません。遅延もほとんどありません。※他の新幹線が遅れる影響で遅延することはあります)。
いつ頃から雪が降りますか?
例年、11月末から12月初旬に初雪が降って、その後は融雪と5〜30センチの積雪を繰り返します(この期間は降った翌日には道路に雪はありません)。そして12月中旬から下旬に1メートル以上の雪が一気に降り、本格的な冬に突入します。この時期の積雪は予想しにくく、雨予報でも翌朝は真っ白ということは多々あります。11月下旬からはスタッドレスタイヤ装着をおすすめします。春は3月中旬に最後のドカ雪があり、その後はほとんど降らないのですが、4月までは降雪予報にご注意ください。
積雪状況を知りたいのですが…。
下記のライブカメラをご覧いただくとリアルな路面状況がわかります。なお里山十帖にいちばん近いのは大沢山のライブカメラですが、県道に雪がなくても里山十帖への道を分岐してから数百メートルの区間に雪がある場合もあります。
関越自動車道の関越トンネルを出たあたり
関越自動車道の湯沢から塩沢インターの間
国道17号線塩沢付近(塩沢インターを出てすぐのあたり)
大沢山(里山十帖のすぐ近くの県道76号線)
大雪予報なのでキャンセルできますか?
代替交通手段がある限り、規定のキャンセル料を頂戴いたします。関越自動車道に通行止めの可能性のあるときは上越新幹線でお越しください。上越新幹線は大雪でも止まりません(在来線はすぐ止まりますので、その際は越後湯沢駅からタクシーをご利用ください)。なお上越新幹線が全面運休した際にはキャンセルチャージをいただきません。
食事について
野菜や山菜が苦手なのですが、違う料理をお願いすることはできますか?
申し訳ございません。ご用意できません。里山十帖では新潟・南魚沼の風土・文化・歴史を表現するためにも、また昔ながらの日本食のバランス(野菜中心で肉・魚を少々)が環境にも身体にも優しいと考えています。野菜や山菜が苦手な方は他の宿泊施設をご検討いただければ幸いです。なお「野菜は嫌いではないけれど、肉をもっと食べたい!」という方には追加料理もご用意しております。
詳しくは、こちらをご覧ください。
日帰り(食事のみ)での利用はできますか?
夕食に限り、日帰りでのご利用を承っております(事前予約制/ご利用可能人数:1名~4名様)。
お時間は17:00スタートのみで、里山十帖コース(16,500円[税込])をご提供いたします。
ご利用希望の場合は前日までにご予約ください。
※ご宿泊のご予約状況によってはご予約をお受けいたしかねる場合がございます。空席状況はお気軽にお問い合わせください。
※ご朝食やご昼食、ご入浴の日帰り利用は受け付けておりません。
ベジタリアン・ヴイーガン・マクロビオティックに対応してもらえますか?
3日前までのご予約で、ベジタリアン、ヴィーガン、マクロビオティックにも対応いたします。
内容により追加料金がかかる場合があります。事前にお問い合わせください。
ただしマクロビオティックは陰陽のバランスまで考えたものではなく、白砂糖、乳製品を使わない玄米菜食メニューとしてご提供します。
個室での食事は可能ですか?
築150年のレセプション棟に特別室が2室、個室が1室あります。
ご利用料金として、飲食代合計の10%をサービス料として頂戴しております。
また古民家部分ではありませんが、プライベートダイニングには個室が5室あり、こちらはサービス料なしでご利用いただけます。ご希望の方はお早めにお申し込みください。
※プライベートダイニングは完全な個室ではありません。隣の音が聞こえますのでご了承ください。詳しくは、「空間について」をご覧ください。
※特別室は201号室・202号室限定で提供している「夕食時の個室確約!記念日プラン」をご予約いただいたお客様を優先してご案内しております。
ノンアルコール・アルコールペアリングは当日注文できますか?
当日ご注文いただくことも可能ですが、前日までにご予約いただくとお得にお楽しみいただけます。 詳細は https://www.satoyama-jujo.com/restaurant/ の「お飲み物」をご覧ください。
追加料理はいつまでに注文したらいいですか?
3日前までにご注文ください。ただし当日ご注文可能な場合もありますので、「あ、注文忘れた」という方はチェックインの際にお尋ねてください。
朝食は何時からですか?
朝食は 7:30 / 8:00 / 9:00 でご用意しております。 ご希望の回をチェックインの際にお伺いします。
貸切での利用は可能ですか?
はい。宿泊利用の場合は全館貸し切りが可能です。企業研修や役員会なども多数行われています。お気軽にご相談ください。
食事の持ち込みはできますか?
里山十帖では「オーガニック」を重要なテーマのひとつにしています。そのためコンビニのお弁当やカップラーメン、ファストフード等の館内へのお持ち込みはご遠慮いただいております。
お酒の持ち込みはできますか?
ワイン、シャンパーニュ、日本酒などのダイニングへのお持ち込みは、グラス使用料として1本あたり3,300円[税込]を頂戴しております。
ルームサービスはありますか?
はい。下記のルームサービスをご用意しております。
自家製おつまみ盛り合せ 1,980円[税込]、おにぎり1,620円[税込]、笹おこわ1,620円[税込]です。
予約について
公式サイトから予約すると特典はありますか?
公式サイトがどこよりも安いベストレートです。さらにご宿泊時に10Stories Hotel(里山十帖、箱根本箱、講 大津百町、松本十帖、尾瀬十帖)で次回以降にご利用いただける割引券5,000円(1名様利用時2,500円)、紹介チケット2,000円(1名様利用時1,000円)をお渡ししております。
リピーターチケットと紹介チケットの内容を確認したいのですが。
■Special Servise Ticket 5,000円割引
・ご宿泊いただいたご本人様に限り有効です。
・2名様以上、1泊2食でご利用の場合、合計宿泊料金より5,000円割引いたします。 (ひとり旅でのご利用の場合は、半額2,500円割引いたします)
・里山十帖公式ホームページまたはお電話での予約に限り有効です。
・Special Servise Ticket は1回のご宿泊につき、1グループ1枚のみご利用いただけます(連泊の場合も1枚のみ)。
・1泊朝食付きやルームチャージでの宿泊にはご利用いただけません。(講大津百町は1泊朝食でご利用いただけます)。
・チェックイン時にスタッフへお渡しください。
・金券ではありません。現金との交換はできません。買い物やお食事のみではご利用いただけません。
・他の割引サービス(紹介チケット等)とは併用できません。
・第三者への譲渡されたチケットは利用不可です。また宿泊記録がない方からご予約いただいた場合には、前回ご宿泊いただいた方とのご関係等をお伺いすることがあります。
・箱根本箱、講 大津百町、松本十帖、尾瀬十帖でもご利用いただけます。
■Special Servise Ticket ご紹介 2,000円割引
・2名様以上、1泊2食でご利用の場合、合計宿泊料金より2,000円割引いたします。 (ひとり旅でのご利用の場合は、半額1,000円割引いたします)
・Special Servise Ticket ご紹介 は1回のご宿泊につき、1グループ1枚のみご利用いただけます(連泊の場合も1枚のみ)。
・里山十帖公式ホームページまたはお電話での予約に限り有効です。
・1泊朝食付きやルームチャージでの宿泊にはご利用いただけません(講大津百町は1泊朝食でご利用いただけます)。
・チェックイン時にスタッフへお渡しください。
・金券ではありません。現金との交換はできません。買い物やお食事のみではご利用いただけません。
・他の割引サービス(紹介チケット等)とは併用できません。
※2室以上でご予約の場合、1室にSpecial Servise Ticket 5,000円割引を、もう1室にSpecial Servise Ticket 紹介 2,000円割引を適用することはできません。
・第三者への譲渡は不可です。 メルカリやヤフオク等で転売されたものであることがわかった場合には無効とさせていただきます。
・箱根本箱、講 大津百町、松本十帖、尾瀬十帖でもご利用いただけます。
お祝いで利用します。何かオプションはありますか?
お祝い用ケーキや花束(有料)、デザートプレート(無料)のご用意が可能です。お部屋にシャンパーニュをご用意すること(有料)も可能ですので、ご相談ください。
予約内容はどこで確認できますか?
各予約サイトのお客様ページにてご予約の詳細を確認できます。
里山十帖公式ホームページからご予約の場合
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/di/?hcod1=67480&hcod2=001&seek=on&def=seek
一休.comからご予約の場合
https://my.ikyu.com/login/confirm/stay/
※電話やメールでご予約の場合はコンシェルジュデスク(info@satoyama-jujo.com)へお問い合わせください。
台風が来ています。キャンセルできますか?
代替交通手段がある限り、規定のキャンセル料を頂戴いたします。関越自動車道が通行止め&上越新幹線も全面運休した際にはキャンセル料は頂戴しません。なお大地震等、天変地異の場合はその限りではありません。
風邪をひいてしまいました。キャンセルできますか?
楽しみにされていたご旅行なのに、心中お察し申し上げます。大変心苦しいのですが、規定のキャンセル料を頂戴いたします。なおご自身が旅行できる状態であれば、里山十帖では風邪をひいていても歓待いたします。雄大な山を眺めながらゆっくりすれば、体調もよくなるかもしれませんよ。
温泉とサウナについて
日帰り入浴はできますか?
昼は清掃時間と重なり、夜はご宿泊のお客様への配慮から受け付けておりません。ご了承ください。
サウナはありますか?
貸切でご利用いただけるサウナがございます。2時間制で一組12,000円(税込)。空き時間がある場合に限り、当日予約も可能です。事前のご予約をおすすめします。
貸切サウナの詳細を教えてください。
ゆっくり温まっていただきたいので、サウナの本場、フィンランドと同じくサウナ室は低めの設定(とはいえフィンランドよりは高めの設定です)。サウナストーブは一回り大きなサウナ室を温められるパワーのあるものですが、座った際の頭部付近で85℃、座面で75℃になるように設定しています。水風呂は、大沢山の湧水かけ流しで15℃前後。サ室は少し小ぶりですが、水風呂&ととのいスペースは巻機山を眺めながらゆったりとお楽しみ頂けます。裸でご利用いただけますが、気になる方は水着をご持参ください。
【定員】2名
【温度】天井で100℃設定(座った際の頭部付近85℃、座面75℃)
【ロウリュ】セルフロウリュ
【水風呂】15℃前後
【ととのいスペース】フラットチェア2台
【使用時間】①14:00-16:00 ②16:30-18:30 ③19:00-21:00 ④21:30-23:30 ⑤7:00-9:00 ⑥9:30-11:30
※14:00~16:00でサウナをご利用の場合は、客室への入室は15:00からとなります。アーリーチェックインの場合は、客室への入室は14:00から可能です。9:30~11:30でご利用の場合は、サウナご利用前にチェックアウトをお願いしております(お荷物はフロントにてお預かりいたします)。
※ご予約は1組1枠(2時間)限りとさせて頂いております。
※水着とサウナハットのご用意はありません。ご自身でお持ちください。ポンチョのご用意はあります。
露天風呂をスマホで撮影してもいいですか?
はい。ただし原則的に「他のお客様がいないとき」に限らせていただきます。とはいえ、朝焼け、夕暮れには息を飲むほどの絶景が現れる時も。そんなとき撮影されたい場合は、必ず他のお客様に了承を得てください。
部屋について
おすすめの客室は?
一番人気の客室は301号室です。人気の理由はコンパクトながら山の眺望が素晴らしいことなのですが、私たちスタッフのおすすめはメゾネットタイプの201と202号室。201にはハンス・ウエグナーのGE290が、202にはミース・ファン・デル・ローエのバルセロナチェアが設置されています。
「201と202、どっちがおすすめ?」と聞かれた際には、明るい雰囲気が好きな方には201、都会的な雰囲気が好きな方には202をおすすめしています。ちなみに窓から見える巻機山(まきはたやま)の景観はわずかに202のほうが上ですが、201は角部屋なので横方向にも窓があります。机が広いのも 201。書類を広げて仕事をするなら201がおすすめです。どちらもファンが多く、「絶対に201!」という方もいらっしゃれば、「202がいい!」という方もいらっしゃいます。ぜひご利用下さい。
アーリーチェックイン、レイトチェックアウトは可能ですか?
はい。アーリーチェックインは14:00、レイトチェックアウトは12:00です。それぞれ1室につき3,300円[税込]でご利用いただけます。アーリーチェックインをご利用の場合は、ご宿泊前日までにご連絡ください。
車椅子の利用はできますか?
あいにく、里山十帖にはエレベーターがなく、古い建物をリノベーションしているため各所に段差と階段があり、車いすをご利用いただけません。杖を館内でご利用いただくことは可能です。
その他
小さな子供がいるのですが、宿泊できますか。また料金はいくらでしょうか。
お子様のご利用は、小学校高学年以上でお願いしております。
小さなお子様につきましては「宿泊のご案内」の「お子様のご利用について」をご参照ください。
小学生以上のお子様の料金は、大人と同じ料金を頂戴し、お食事やアメニティも大人と同じ内容でご用意いたします。
なお、夕食をキッズプレートに変更することも可能ですので、事前にご相談ください。
乳幼児のお子様で添い寝でのご利用の場合、ご宿泊代は無料です。
ご夕食は3,300円[税込]のキッズプレート、ご朝食は大人と同じメニューを5,500円[税込] で、ご希望に応じて用意いたします。(事前予約制)
事前に荷物を送ることはできますか?
はい。事前に荷物を送られる際は、下記の住所へお送りください。
〒949-6361新潟県南魚沼市大沢1029-6 フロント宛
※ご配送の際は、伝票に宿泊日とご宿泊代表者様の氏名をご記載ください。
たばこの煙と臭いが苦手です。禁煙室をお願いできますか?
ご安心ください。客室内のテラス・ベランダも含めて全館禁煙です。
周辺環境と季節について
南魚沼はどんなところですか?
標高2000メートルの山々が眼前に聳える、北アルプスにも負けない素晴らしい自然環境です。北アルプスは標高3000 メートル、魚沼は2000メートル。その差は大きいように思えますが、麓の標高は南魚沼160メートル、白馬700メートル。「標高差」で比べると実はそれほど変わりません。実は無名なだけで日本有数の絶景を楽しめる場所なのです。
どの季節がおすすめですか?
「全てです!」と言いたいところではありますが、いちばん里山十帖の周辺が輝くのは残雪と新緑のコントラストが美しい時期。例年、ゴールデンウィーク後半、5月5日前後に新緑が始まり、ゴールデンウィークが明けた直後、5月10日〜20日が最も美しい季節です。この時期の美しさは言葉に形容できないほどで、多くのスタッフが「この季節の景色を見るためにだけにこの地に住んでいる」というほどです。さらに6月初旬までは新緑の色が毎日異なるほどドラマチックで、5月20日ごろになると水田の水鏡に山々が映り、その素晴らしい景観が6月10日ごろまで続きます。秋の紅葉も素晴らしく、見頃は10月20日〜11月15日ごろ。植生の違いもあって、関越トンネルの向こう側、群馬県とはまったく違う色合いの紅葉が楽しめます。そしてリピーターの方に大人気なのが12月末から3月10日ごろ、雪しかない時期。1月末には3メートル以上の雪に覆われ、雪が全ての音を吸収してしまいます。都会ではあり得ない「無音」の空間。静寂の時間を楽しむために連泊する方が多いのもこの季節です。そして3月10日から3月末は冬と春が交互に訪れ、連泊するとダイナミックな季節の変わり目を楽しめる時期。周囲は3メートル近い雪が残るのに鳥の鳴き声が聞こえ、森の香りが里山十帖周辺に充満します。
山菜料理はいつ頃ですか?
里山十帖の看板とも言える山菜料理をご提供するのは、里山がもっとも輝く新緑の時期。3月中旬、雪の下で育つフキノトウのご提供から始まり、ヤブカンゾウ、アサツキなどに続いて、5月10日から5月末にピークを迎えます。もっとも山菜の種類が多いのも5月10日前後からの2週間。その後、名残の山菜料理が6月下旬まで続きます。
発酵食品を食べたいのですが、いつ頃がいいですか?
冬にお越しください。山菜料理と同じくらい、人気が高いのが発酵・保存食。作業は雪解け直後から始まります。次の冬を越すためにゼンマイを干し、ワラビを乾燥させて、ウドを塩漬けにして…。夏にも野菜を乾燥させたり塩漬けにして、作業のピーク、秋を迎えます。沢庵をはじめ、たくさんの漬物を仕込むほか、麹漬けや天然酵母による発酵食品もたくさん仕込みます。この時期、地下の発酵蔵は置き場もないほどいっぱいになります。また雪室を組み立て、降雪直前に採れたニンジンや大根、ハクサイ、ジャガイモなどの冬野菜を雪室に貯蔵します。これらの保存食、発酵食をご提供するのは「冬限定」。よく「里山十帖は発酵食が有名と聞いてきたのに、ぜんぜん発酵食が出ませんね」とご意見を頂戴するのですが、発酵食は冬を越すための雪国の知恵。近年、「発酵」は世界的ブームになり、旨みを引き出すための発酵機を使った発酵がレストランでもブームになっていますが、里山十帖では行いません。発酵・保存食をご希望の方はぜひ冬にお越しください。
紅葉はいつ頃ですか?
天候や気温にもよりますが、10月中旬から11月中旬が見頃です。10月に入ると周辺に聳える2000メートル前後の山々で紅葉が始まり、平均すると1日で標高60メートルずつ紅葉の帯が里に向かって下りてきます。10月中旬には初冠雪して山頂部は雪、中腹が紅葉、里山は緑という「三段紅葉」が見られることも。そして11月に入ると里山十帖周辺の木々が紅葉します。なお周辺の紅葉名所のピークはおおよそ下記の通りです。
谷川岳天神平ロープウェイ 10月10日〜20日ごろ
ドラゴンドラ 10月15日〜25日ごろ
湯沢高原パノラマパーク 10月20日〜30日ごろ
トレッキング湯沢1 10月20日〜30日ごろ
銀山平と枝折峠 10月15日〜25日ごろ
奥只見湖 10月20日〜30日ごろ
魚沼スカイライン 10月25日〜11月5日ごろ
里山十帖周辺 11月15日前後
美人林 11月10〜20日ごろ
雪景色を見るならいつがいいですか?
年によって前後しますが、11月末ごろから降っては溶けてを繰り返して、12月10日〜20日頃、一気に1メートル以上の積雪になります。「チェックインした時には雪がなかったのに、チェックアウトするときには1メートル近い雪」というドラマチックな景色を楽しみたいならこの時期を狙ってください。その後、積雪は増えたり、減ったりを繰り返しながらピークに達するのは2月中旬〜下旬。例年、1月末で2メートルを突破。ピーク時には3メートル、最も多い年は6メートルを超えました。そんな時でも上越新幹線は1分の遅れもなく運行しています(遅れが発生する時は山形新幹線と秋田新幹線に起因することがほとんどです)。大雪予報でも新幹線と定額タクシーをご利用いただければ、安心してお越しいただけます。なお積雪は例年4月中旬まで残ります。
蛍はいつ頃見られますか?
天候によりますが、例年7月上旬から中旬、場合によっては7月下旬まで蛍が舞っています。ときには露天風呂まで飛んでくることも。梅雨時期ですが、7月上旬の新潟・南魚沼は地形の関係で意外と晴れている日が多いのです。晴れた日には満天の星空と天の川。蛍との共演をお楽しみください。
おすすめの観光スポットはありますか?
こちらのMAPにおすすめスポットをまとめています。ぜひご覧ください。
アクティビティーはどんなプログラムがありますか?
■早苗饗 -SANABURI- キッチンorガーデンツアー (毎日・無料)
ご夕食を17:00の回でご予約いただいたお客様を対象に、料理を担当するフードクリエイターがご案内するツアーを行なっています。 春から秋は宿の周辺を歩きながら、この土地の植生についてお話ししたり、ハーブガーデンを見学して料理に使う自家製ハーブを摘んだり。 秋から春先は保存食を貯蔵する雪室や発酵部屋を見学したり、裏山の山野草を摘んでもらったり……。 ツアーの最後には、季節の食材を使ったフィンガーフードやオリジナルドリンクでの「アペリティフタイム」をお過ごしいただいて、そのままご夕食をお楽しみいただきます。 ご参加ご希望の方は、予約時の問い合わせ欄に参加希望とご記載いただくか、チェックインの際にスタッフへお声がけください。
■絶景・早朝サイクリングツアー[6月上旬〜11月中旬・おひとり13,200円]
里山十帖の人気アクティビティ「早朝サイクリングツアー」。 車で標高920メートルの絶景スポット「魚沼展望台」までお連れして、そこからクロスバイクで下ります。 春と秋は眼下が雲海で埋め尽くされることも多く、特に10月〜11月は雲海発生確率70%以上。正面には標高2000メートルの山々が並び、息を呑むほどの美しさです。車に自転車を積んでいくので、お客様の登りはゼロ。舗装路を降りてくるので、ケガの心配もほとんどありません。自転車が乗れる方ならどなたでも体験可能です。
催行時間:6:00〜8:00(基本的に3日前までのご予約制)
おひとり様13,200円(里山十帖オリジナルタンブラーとドリンク付き)。
先着順で定員5名まで(催行人数2名〜)
※ガイドの休日により、お申込みいただいてもご希望に添えないことがあります。
※当日は晴れていても路面凍結など、走行に危険な日は中止することがあります。
※長袖、長ズボン、スニーカーなど動きやすい服装でご参加ください。
■早朝スノーシューツアー [1月下旬〜3月下旬・おひとり9,900円]
大人気アクティビティ、里山十帖の裏山を散策するスノーシューツアー。 早朝の日の出前にスタート(6:30頃)して絶景ポイントへご案内します。 運が良ければ一面の雲海や日の出がご覧いただけます。ホットドリンクとスノーウェア付き。
催行時間:6:30〜8:30(基本的に3日前までのご予約制)
おひとり様9,900円(ウェア・グローブ・帽子・長靴のレンタルあり・1名から催行可)
※ガイドの休日により、お申込みいただいてもご希望に添えないことがあります。
※悪天候時には中止いたします。